藤原宏美さんと関水徹平さんの著作『独身・無職者のリアル』(扶桑社)がキンドル版になりました。7月25日から31日までは、半額キャンペーンが実施され、通常600円が300円で買えます。
ついでですが私の『ひきこもり当事者と家族の出口』(子どもの未来社)も電子書籍になっています。*作者名:五十田猛 通常価格:540円(税込) 、[参考]紙の本:864円(税込)。
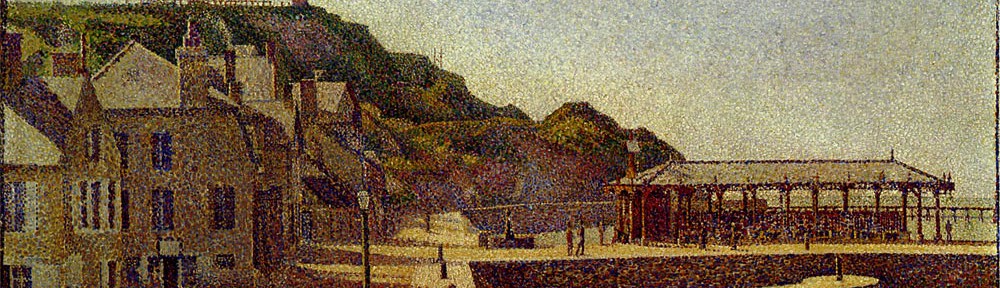
藤原宏美さんと関水徹平さんの著作『独身・無職者のリアル』(扶桑社)がキンドル版になりました。7月25日から31日までは、半額キャンペーンが実施され、通常600円が300円で買えます。
ついでですが私の『ひきこもり当事者と家族の出口』(子どもの未来社)も電子書籍になっています。*作者名:五十田猛 通常価格:540円(税込) 、[参考]紙の本:864円(税込)。
発達障害の当事者でワークショップをひんぱんに開いている冠地情(東京都成人発達障害者当事者の会イイトコサガシ代表)さんから連絡がありました。
105分のDVD「発達障害の人の可能性を広げようー人間関係を変えるコミュニケーション」を発行したのでその宣伝チラシを配布してほしいというものです。
DVDは地域精神保健福祉機構(コンボ)制作で、定価3500円+税。
またメンタルヘルスマガジン『こころの元気+』11月号は480円です。
注文先は地域精神保健福祉機構(コンボ)書籍係:
〒272-0031 千葉県市川市平田3-5-1、
FAX047-320-3871
本・DVDは郵便振替用紙(料金支払い用)と一緒にお送りするようです。
 子どもの未来社から『ひきこもり 当事者と家族の出口』(2006年)という新書版を発行していただいています。その本を電子出版にするように案内が送られてきました。出版物が電子出版に広がっていく時代をこのような形で実感するわけです。
子どもの未来社から『ひきこもり 当事者と家族の出口』(2006年)という新書版を発行していただいています。その本を電子出版にするように案内が送られてきました。出版物が電子出版に広がっていく時代をこのような形で実感するわけです。
「本著作物の全部または一部と同一もしくは明らかに類似すると認められる内容の著作物を、…自ら運営するホームページ(ブログ、メールマガジン等を含む)において利用しようとする場合においては、事前に通知し、同意を得なくてはならない」ということになります。そうたいした決め事ではないです。上の本は私の手元にも数部は残っています。先日もどこかに書いたように自ら販売する努力もしなくてはなりません。1冊840円プラス送料160円です。よろしくお願いいたします。
「不登校と子どもの成長」セミナーを始めます。
池袋の会場で9月から毎月1回の学習会をします。田中登志道『不登校からの出発』佼成出版社、2009年、定価(1200円+税)を共通のテキストとします。
参加対象者は、不登校の子どもの親(小・中・高校など)、カウンセラー・支援者になりたい人です。10名ぐらいまでを募集します。
毎回テキストを読み、質疑・応答とその後の自由討論です。セミナー学習のあと、希望があれば個別の相談をします。親の相談を優先します。このテキストによるセミナーは12回程度(1年)を予定しています。可能な人はテキストを読んできてください。
参加申込みは不登校情報センターまで「不登校セミナーに参加希望」と申し込んでください。参加費は1回500円です(TEL:03-3654-0181、FAX:03-3654-0979、メール:open@futoko.info)。テキストをお持ちでない人には、次回セミナーの範囲をコピーして渡します。
日時は未定ですが平日夜間か土日曜日の午後で調整中です。
会場はSES教育研究所(豊島区南池袋2-48-2 セザール池袋2F、「池袋」駅東口10分)。
大阪で活動をしている「中卒・中退の子どもをもつ親のネットワーク」から会報が送られてきました。
会報名は会名と同じで、227号になります(たぶん20年ぐらいの活動歴)。
内容は、同会の定例会の案内ですが、大部分は同会に寄せられたいろいろな便り・案内類です。
かなり以前にも何度か送っていただいていますがこの点は同じです。
大阪で活動していますので、関西方面のイベント情報がわかります。
さっそく「イベント情報」に6件を掲載しました。
あわせて今後とも情報入手の方法として送っていただくようにお願いしました。
社会福祉法人いのちの電話から 『インターネット相談報告書』を送っていただきました。
報告書の内容は自殺予防の立場からの現状や取り組みが中心です。
不登校情報センターのサイトを見られている方にもその情報提供は有効に役立つものと思います。
「いのちの電話」は相談電話以外にもネット相談をしていることがわかりました。
相談先の電話・ネット一覧を送っていただき、適当な形で掲載していこうと考えたところです。
近くこの線に沿った返事をするつもりです。
『グーグルに異議あり!』(明石昇二郎、集英社新書、2010年)と『ネット帝国主義と日本の敗北ー搾取されるカネと文化』(岸博幸、幻冬舎新書、2010年)を読みました。
発行時期は近いし、グーグルを中心対象にする点は同じです。
社会に強烈な重力のある物が入ってきて周囲がその影響下にいる状況を描いています。前者は体当たり的な実行記録、後者は全体を眺めて問題点と対応策を紹介するものです。
詳しいことは省略しますが、後者の本ではグーグルをトップとするネットレイヤー構造の「プラットフォーム」部隊は流通手段であり、ネット経済社会で最大の利益を得ている。コンテンツ部隊である文化や新聞が危機に追い込まれている。そこでコンテンツ部分をバックアップしなくてはならず、それは自助努力と不公平なシステム是正が大事なようです。
不登校情報センターのサイト制作も、超微細ながらコンテンツ部分です。
日本におけるコンテンツ再生化のチャンスを3つ上げていて、その一つが「地方メディア」です。私はこれを都合よく「専門的な業界メディア」と置き換えて考えることにしました。
本の書名は無理をしています。そう強がらなくてもよかったし、サブタイトルは浮いています。
親の会のDさんが読み終えたからといって引きこもり関係の本を持ってきてくれました。
足立倫行『親と離れて「ひと」となる』NHK出版。
川口和正ほか『ひきこもり支援ガイド』晶文社。
諸星ノア『ひきこもりセキラララ』草思社。
武藤清栄ほか『ひきこもり脱出ガイド』明石書店。
石川良子『ひきこもりの〈ゴール〉』青弓社。
斎藤環『ひきこもりはなぜ「治る」のか?』中央法規。
田辺裕・ブックマン社編『私がひきこもった理由』ブックマン社。
以上の7冊です。最後の2冊は、センター内には置いていなかったと思います。
不登校、引きこもり、発達障害と周辺事情に関係する本で、捨てるしかない時は、こちらに譲ってください。
ただし取りにはいけませんので、持って来ていただくかお金を負担して送っていただくかでお願いします。
これらの本を貸し出ししたいのですが、体制が整いません。
それで来たときに読みたい本が見つかればお貸しすることにしています。
神奈川県立青少年センター青少年サポート課から『ひきこもりーひとりで悩まないで』というA5版16ページのリーフレットを送っていただきました。
このなかにたぶん監修者の山田正夫精神科医のものでしょうが、引きこもりに関する定義づけがあります。
「ひきこもりとは病名ではなく、さまざまな要因によって社会的な参加の場面がせばまり、
自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことをさします」となっています。
このブログで紹介した卒業論文のSさんは、引きこもりを「自らの意志で不安を回避するための措置としてこもったにも関わらず、
何らかの要因に阻まれてそこから自力で社会へ戻ることが出来ないうちに時間ばかりが過ぎていってしまう問題」と見ます。
どちらがより正しいというのではなく、それぞれが正しいと思います。むしろおもしろく感じるのは評価する人、判断する人の価値観や立場が現れているように思います。
その視点に立って、引きこもりに関するいろいろな定義の仕方を集めてみるのもおもしろいかも…と感じました。
訪問サポート・トカネットに参加しているDさんが、卒業論文を見せてくれました。
テーマは「ひきこもり支援」に関するものです。40字×40行・A4版23ページなので400字原稿換算100枚近くです。
引きこもりの支援というとき、対人関係がない、社会経験がない、職業的な技術がない、だからその力を身につけていくのが支援という考え方があります。
それに頼る方法は対象者が限られ、引きこもっている人が発する基本的なメッセージを素通りしている感じがします。
私は引きこもりとは大きな時代の変化、単純な言い方をすれば産業社会から情報社会への歴史的な移行期に際して、
感覚のすぐれた若い世代がその正体をよくつかみきれないまま心身状態で未来を探している面があると思ってきました。
しかし、それはなぜなのか、それをいかに表現すればいいのかは極めて不十分な状態におかれています。
Dさんの卒業論文にはそれに対する、自分の実践と自分自身の感覚と洞察による一つの回答が与えられています。
それを以下のような言葉で表現できたことは、Dさんの感受性と洞察力の素晴らしによるものと思います。
引きこもりとは何か。彼はある中心点をとらえていますが、いくつかの表現をしています。
「自らを縛る意識によってもたらされる息苦しさ」(3ページ)を持つ人であり、
「自らの意志で不安を回避するための措置としてこもったにも関わらず、何らかの要因に阻まれてそこから自力で社会へ戻ることが出来ないうちに時間ばかりが過ぎていってしまう問題」(4ページ)と見ます。
引きこもっている当事者はこの状態を「無駄な時間で何の役にも立たない経験」(1ページ)と意識します。
Dさんは引きこもりのもつ状況を「これは私自身の問題」(1ページ)ととらえています。この点はこの卒業論文を現代の青年論にしています。
Dさんは訪問支援の実践を通して何がわかったのか。訪問支援者がしていることは、当事者が自分を拘束している「規範意識の呪縛から彼らが解放されるための手助け」(19-20ページ)であり、引きこもる人は「自身の価値観を確立する」ことで事態を乗り切るのです。しかしそれは一人ではでき難く、そこに訪問支援者の役割があります。
それに先立ち、家族の役割が作用します(Dさんの実践例では家族の変化が見られる。一般には家族が家族以外の人の支援を求める姿勢の変化があります)。
訪問支援者は「彼らの人生の中ではほんの一瞬」関わりながら、彼らの無駄と思っていることを意味のある作業にし、業績にまでするのです。だから引きこもる人に手出しをせずに横にいる、問われたことに自分の感覚で答えようとする、訪問支援者は「何をする」のかと問われたら「特に何かをするのではなく一緒にいる」という禅問答のようになるのです。
引きこもりという彼らの作業とは、葛藤することであり、体験の振り返りであり、模索することです。
彼らの業績とは「引きこもり体験者」という“洗礼”を経験したことで、たとえば臨床心理士と並んで引きこもりを理解している人として有効な役割をすることです。
引きこもりとは、これまでの社会の規範意識の束縛から自ら解放するための闘いの状態像です。自身一人が価値観を確立するために闘っているように見えても、その集合体は社会の新しい規範の確立に結びつくのです(青年論としてみれば特にその面ははっきりと出ます)。
これまで私がつかみかね、表現できなかったことへのある種の回答を与えられた気持ちになるのはこの点です。
社会の新しい規範がどのようなものになるのかはまだこれからですが、情報社会に照応する、人間がそこで生きるのにふさわしい条件を用意するものになるのでしょう。
だから引きこもりには意味があり、業績にもなるのです。
とはいえ、引きこもりの状態は実にさまざまです。
人間はある方向に進みますが正確な一本道をたどるのではなく各人が試行錯誤をしながらある方向に収斂し、しかもなお多様性を示していきます。
多くの状態があるのはそのためですし、それは引きこもりだけではありません。
多くの社会現象もまたさまざまな様子を示すことが予測されるのです。
いろいろな分野で時間幅はあるけれども同時的にこれまでは見られなかったことが生じています。
それは社会的なことに限らず、もしかしたら自然現象までも伴うのかもしれません。
このなかに共時性なる何らかの法則性が見られるのかもしれません。
私のこの感想文はさらに推敲をして、「五十田猛・論文とエッセイ」ページに載せる予定です。