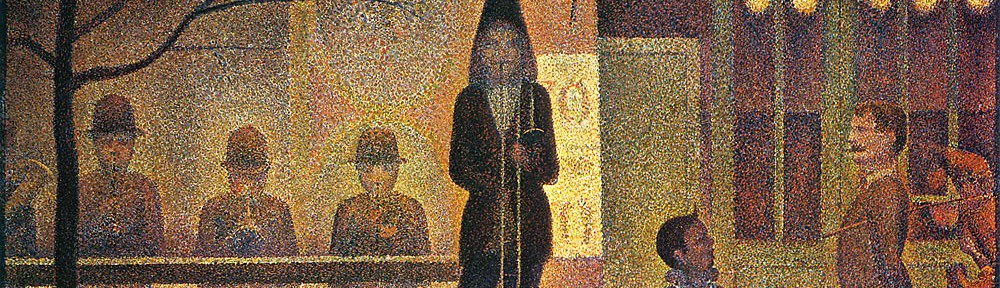ひきこもりの支援活動の基本は社会参加の現実的な基盤をつくることです。
現在のひきこもり支援策がいろいろあるといいますが、大きく分けると私は三つになると考えています。
(1)地域若者サポートステーションに代表される支援団体です。直接の就職支援をする機関で、支援団体はそのための訓練施設です。仕事上の知識や技術を身につける訓練からはじまり、その延長として対人関係の訓練などを含むように広がってきました。支援の向かう先は主に就職になります。支援団体という訓練施設のタイプは学校型の支援と考えます。
(2)第二のタイプは、福祉型に向かいます。ひきこもりの当事者がもつのは家族関係とか対人関係などの問題と考えます。ところが友達関係や家族関係の改善が社会参加や仕事につくことと結びつかない様子があります。事情にはひきこもりの長期化と当事者の高年齢化が関係しています。
こちらの取り組みは、ひきこもりである状態を一種の障害と認め、広い意味の障害者への社会福祉型の支援枠に向かっています。
(3)上の二つのタイプがひきこもり支援の中心です。
ところがこれらの支援方法は行き詰まるのではないかと思うのが第三に道を必要とする背景です。その視点から不登校情報センターの当事者の居場所、そこにおける作業の発生から現在までの十年以上の取り組みを振り返ったのが本書です。
ひきこもり個々人がばらばらに就職ないしは社会参加に向かうのではなく集団的な自立をめざします。この集団的な場が会社ではなくNPOです。
その場は一つの営業単位です。その営業単位がどの程度の収益を獲得するかによって構成メンバーの収入も変わります。実例に挙げるのは不登校情報センターというNPOですが、ここ自体は収益赤字です。
その場は営業単位ですが、発展すれば何らかの共同的な生活の場になるかもしれません。そこはまだ雰囲気として感じるだけです。この居場所ワークがひきこもり支援の決定的な方法と強弁する根拠はありません。別の方法として考える材料にしていただきたいものです。
第二章はこれまでの経過のときどきに書いたものです。今日の取り組みを実務的にまとめた第一章とすぐには結びつかないこともあります。しかしこういう背景があるから今日の姿が生まれたことを考えなくてはよくわからないと思いました。
本格的には重複なく書き下ろすのがいいわけですが、そういう余裕がないなかでまとめたものです。