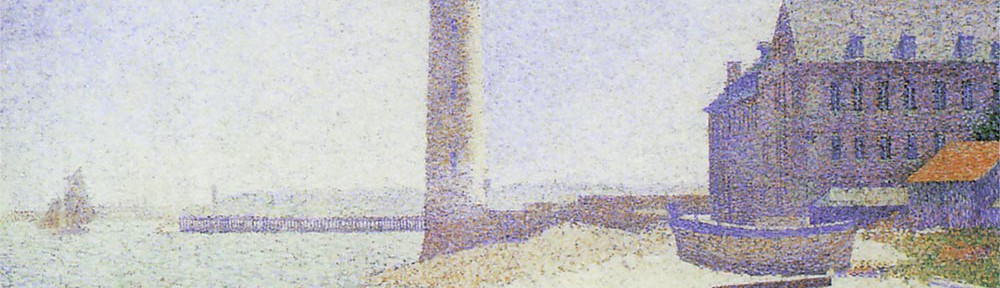ひきこもり大学下町の感想をつづけます。「居場所」分科会でのことです。Skypeの話から、動画サイトのなかで人とつながる話に移りました。
自分で動画サイトに発信している人が、「見ている人数はわかるけれども、感想を書き込まない人がいるのが気になって、動画サイトをやめた」例を紹介しました。引きこもった経験のある人が「わかるような気がする」と答えました。反応する人よりも反応しない人が気になる、というのは引きこもり経験のある人からよく聞くことです。
このような“当事者”ならわかるが、“専門家”にはわかりづらいことは多くあります。“当事者”は“専門家”よりも具体的な知識・感覚があります。これは大事な点で、私はこのような確認をよくします。“当事者”の個人体験に限られ、全体構造をとらえない点が違うのですが、いろんな面に表われます。
講師のちはりさんは、ファシリテーターとして「ひきこもりフューチャーセッション」にかかわり、一般人として引きこもりを話しました。これという予備知識がない中で引きこもりに関わるごく自然なスタンスです。“支援者”と“被支援者”をフラットな関係においた経験を話されました(それだけでも素晴らしいのです)。それは私が“当事者”と“専門家”の関係で見ていることの別表現になっていると理解できます。
一般人がこのように感じる機会は、今の日本にはいっぱいあります。障害者、疾病者、介護受給者、被害者(災害・犯罪)、買い物難民、貧困生活者…などいずれも“当事者”です。そしてこれらの人はそこで問題を実際に体験・遭遇し、事情に通じる専門性もあります。わかっている、ただ多くの人には打開する力がないのです。
“専門家”もこれらの人から教えてもらわなくては打開策がみつかりません。“当事者”と“専門家”、または“支援者”と“被支援者”の関係をこの立場から見直す必要があります。以前からそういう必要性はあったのです。この国でこの機運が高まっているのが現在の歴史的な状況です。
いつから始まったのか。311後の原発反対の行動からと言えます。平和的で粘り強い意思表示は原発反対だけではなく、いろんな形で表われています。これらは“当事者”を含む多くの人ですが、“当事者”にも広がっています。SNSの普及が1つの背景でしょう。
そういうなかで“引きこもり”はどのような当事者なのか。……かなり支援の側に移りやすい経験者というのが私の感想です。これを意外と思う人もいるでしょうが、実感です。
引きこもりを支援する側からの言葉にはその支援の難しさが語られます。受け身であり責任を感じすぎて自分からは何もしないタイプが多いのです。そういう面はあります。例えば、身体障害の人は意思を明確に示しますが、自分ではできないことが多いです。引きこもりは、事態はわかっているけれども自分に降りかかるのを避けようとして押し黙ります。こういう困難さは承知して言いましょう。
引きこもり支援に関心を寄せる引きこもり経験者はかなり多いです。実際の行動に出る人も徐々に増えています。この割合が他のタイプの“当事者”と比べると多いと感じるのです(災害被害者はそれを超えるでしょうが、基本的には一時的です)。引きこもりへの訪問サポートをする登録説明に数人が参加すれば、不登校や引きこもりの経験者がいて、ときには半数以上になります。今回の「居場所」分科会に出席した中にも「居場所をつくりたい」という“当事者”がいました。
抽象的レベルですが、これが今回のひきこもり大学下町のなかで感じた最大の事柄です。企画・主宰したSくんも“支援者”になるのを意識しない、意図しない“当事者”です。