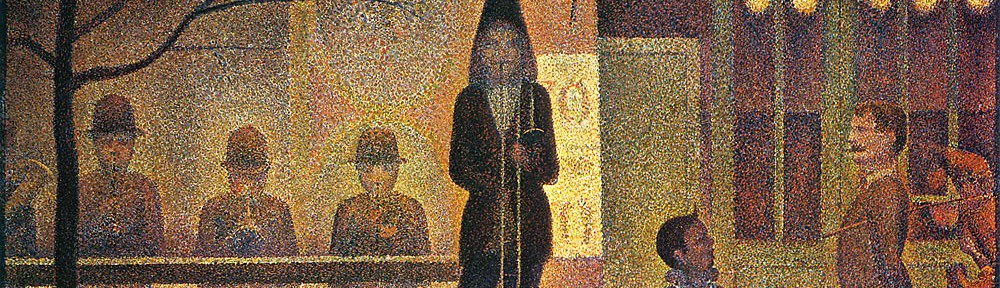『葛飾区子ども・若者に関する調査結果報告書』ができました(6月)。
子ども・若者育成支援推進法(いわゆる子若法)を実施する計画策定のためのものです。
昨年全国の自治体で実施された子どもの貧困の実態調査とは異なりますが、内容は重なる部分もあります。
18歳以上の若者が独自の対象に含まれているのが、ほかの自治体調査とは異なります。
調査は2018年2月に行われました。集計は早いと思います。
対象者は未就学児(保護者)1400名に発送して回答は723件、小学2年生(保護者)1400名で回答は727件、小学5年生(本人と保護者)1400名で回答は655件、中学2年生(本人と保護者)1400名で回答は本人644件、保護者655件、高校2年生になる年齢(本人と保護者)1400名で回答は本人423件、保護者461件、若者(18歳以上39歳以下の本人)1500件で回答は457件。
報告書はかつしか子ども・若者応援ネットワークの全体会(7月17日、参加者は10名ほど)の場で簡単な説明を受け、質疑がされました。
この場で194ページの内容を読むことはできませんのでごく概略的な質疑です。
この調査の実施前に要望していた、本人と保護者に分けてアンケートを送るときは可能な範囲で分ける点、所得による回答をできるだけ分けるクロス発表にする点などを確認する意見が出ました。
私は若者が対象になっている点が評価できること、そのうちひきこもり状態の人からの回答が少ない点(それは避けられない)を考えて、計画策定はそこをカバーするものがないと、空振りの計画になる点を注文しました。
年間家計収入を見ると、300万未満、300万~500万円、500万~700万円、700万~900万円、900万円以上、に分けられています。
貧困問題を見る場合には平均所得100万円以下や100~200万円を分けて状態を調査していますが、子若法による調査はこれとは別のものになります。
葛飾区の報告書では18歳以上の若者を除く回答(本人保護・保護者)の内訳は
100万円未満が1.4%~1.7%、100万~200万円が2.4%~4.2%です(8ページ)。
この分布は実態を反映していると思えます。
クロス調査は低収入者の様子を明らかにしながら他との比較対照出来ることを期待したわけです。
300万円以下一律では期待できづらいですね。
18歳以上の若者の調査結果は、回答者の状況が大きく作用します(67ページ)。
正規の会社員等が52.7%、学生10.1%…とあり、働いておらず・求職活動をしていない1.5%、働いていないが、求職活動をしている1.5%です。
ニート、ひきこもりなど大きな課題のある若者の場合はこの働いていない人の様子を明らかにすることから始まります。
この調査結果をもとに計画を作成しても空振りになるのは回答者数の少なさによります。
該当者の実態をあまり反映しないでしょう。
18歳以上の人の状態や要望が115~119ページに紹介されています。
いろいろな相談・訓練などの施設や機会が示されています。
しかし、これらが対人関係つくりの場所とは扱われていません。
当事者による居場所が広がっているなかで、行政として関わることは無理なのか、そういう視点がないためなのか。
この報告書に手掛かりがみつかるのか、詳しく読んでみることにします。