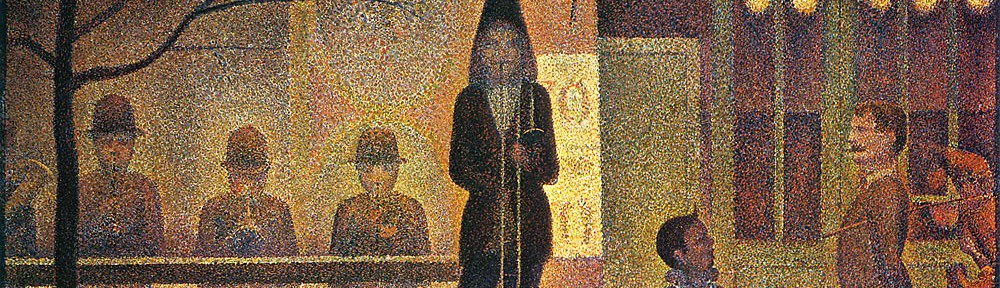かつしか進路フェア2018に相談員として参加しました(8月4日)。
相談コーナーは充実しました。かつしか子若ネット世話人の賜物です。後日聞けると思いますが相談者は数十名になるでしょう。
教育費助成などは社会福祉協議会から、心理や家族関係はスクールカウンセラーが数名交代で、それぞれ一角を占めます。
進路相談というべき「なんでも相談」役も数名が交代で、私はここが担当です。
翼学院さんは3名が始めから終わりまでズーッと相談を受けていました。
かつしか子若ネットのメンバーで、相談の種類・内容の役割がつかめずにいた人もいてこれは今後のテーマでしょう。
私は昨年につづいて「不登校・中退生のための高校案内」を提供しました。
参加者は約3000名といいますが、スタッフを含めて多くの方にこの4ページの案内が配られました。
さらにわかりやすく説明を改善したいと思います。
参加校は100校を超えましたが、別に学校案内パンフ提供が2校ありました。
これに私が預かった6校(寮制の全日制高校、通信制高校、発達障害を受け入れる技能連携校など)の案内パンフを加えました。
この学校案内パンフ提供は大きな前進が見込まれます。
来年からは、寮制の全日制高校、通信制高校など「不登校・中退生のための高校案内」で紹介している学校を「かつしか進路フェア」実行委員会本部から直接に連絡していただく道ができそうです。
私はその学校のリスト案をつくり、かつしか子若ネットのメンバーで検討して、資料参加(学校案内パンフ)をお願いする学校を確定します。
「かつしか進路フェア」実行委員会本部から連絡する形に移行できそうです。
おそらく自治体(教育委員会)が関与し民間の実行委員会が開催する大規模な進路相談会に、「不登校・中退生」の進路相談コーナーが公式に加わる状況になるでしょう。
以前にセシオン杉並で開いていた進路相談会に不登校情報センターが持ち込んだこの種の学校案内は100校程度ありました。
それを一気に進めるよしあしも含めて考えながら、今回の前進を生かしたいと思います。
http://www.futoko.info/zzmediawiki/不登校・中退生のための高校案内