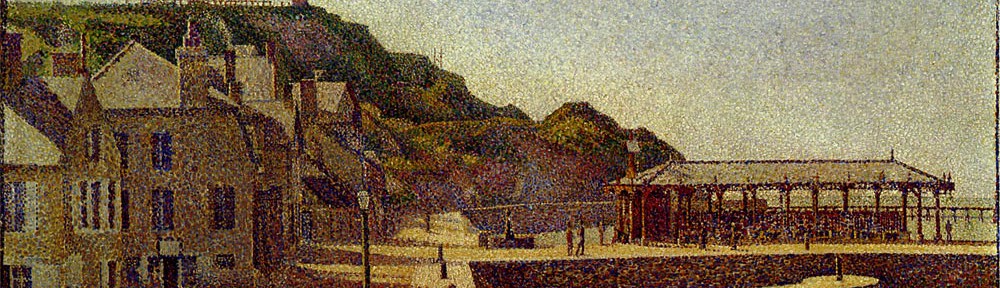14年前の2002年に「不登校情報センターを働ける場にしてください」という10人ほどの要望に「小遣い程度を得られる場にしよう」と答えて始まったのが、現在の居場所ワークです。
始まったころはポスティング(情報誌『ぱど』配布など)やDM(学校案内書のダイレクトメール)の作業が中心でした。そのうち並行して進めていた不登校情報センターの学校や支援団体の情報提供サイト制作の役割が時間とともに大きくなりました。今ではほぼ情報提供サイト制作と運営だけになっています。
3年前からはサイト制作に必要な情報収集を事務作業として始めました。居場所ワークはサイト制作とその情報収集の事務作業の2つになりました。
その事務作業の内容も広がりつつあります。たとえば新分野の情報を集めようとするとき私はメンバーから意見を聞くことが多くなりました。そうすると事務作業グループが企画検討会になります。引きこもりなどを経験した当事者の意見はリアル感が違います。
2015年11月から全国の教育委員会あてに不登校への対応を情報提供依頼しました。このグループの意見を取り入れた依頼内容はよかったと思います。問いかけることが具体的であり、答えやすくなったのです。
サイト制作を始めて数年後から広告収入が得られるようになりました。情報センターとして収入を得、サイト制作にかかわる人にわずかですが作業費を支払う形をとりました。しかしサイト制作・運営業で収益を得ることは難しい課題です。不登校情報センターがその最下段にたどり着いたのは、やっと数年前です。信頼性が高くきわめて規模の大きなサイトに成長しました。
それでも公的な支援は期待できません。いろいろな引きこもり支援団体が活動休止に追い込まれているなかで、このサイトを所有できたことは幸運です。
しかし、今のサイト制作の方法では当事者にとっては自分の収入源にはなりません。不登校情報センターのサイトを活用しながら、各自で収入を得られる運用方法を研究するのが現在の課題です。その研究中の具体例を挙げてみます。
(1)当事者が独自に活用した最初は個人ブログです。不登校情報センターが運営するブログは無料使用できます。そしてブログを書く人が得られる収入(これも広告収入)の大部分を得られるようにしました。しかし、そのレベルで活用できているのはまだ2名にすぎません。収入はわずかです(商業運営のブログは無料で活用できますが、収入を得るレベルになるのは至難です)。
(2)次も広告の一種ですがアフィリエイトと呼ばれます(有名なのはAmazon)。7、8年前に不登校情報センターが広告会社Amazonと契約しました。ここ数年は放置していましたが、昨年秋から活用を再開しました。これはまだ十分な収入レベルではありませんが貢献が期待できます。
当事者が独自に活用できるのは、この運用を別のアフィリエイト会社に応用する形です。契約すればその担当者の収入にできます。そうしながら運用のしかたを学ぶのです。不登校情報センターのサイトは大きいのでそれが可能な状態です。
(3)パソコンのハード面に詳しい人がいます。以前から不登校情報センターのパソコンの管理や修理をお願いしています。ときおり協力者などから「パソコンの動きが遅い」などの話があり、出かけて行って点検・修理をしています。これはヘルプデスクという仕事です。
この人の取り組みを個人バナー広告にしてサイト内の数か所に張り出しました。個人の活動をバナー広告の形で応援する“仕事づくり”です。
(4)文通で相談活動をする人もいます。カウンセリングに近いもので、引きこもり経験を生かした取り組みです。この人の取り組みも個人バナー広告でサイト内に張り出しました。
サイトに紹介している支援団体としてのカウンセラーのなかには、もともとは引きこもり的と思える人もいます。この人たちにも同様の個人バナー広告を案内し始めました。
(5)以前に通所していた人でアクセサリー手作り作品を制作し、自作のホームページで販売をしている人がいます。この人にも個人バナー広告の案内をしています。販売上の手助けに利用してもらうのです。このタイプの人は他にもいると予想しています。
個人バナー広告は、引きこもり経験者によく表れる職業指向(カウンセリングなどの対個人サービス系、手芸などの創作活動系)を応援していく役割がみてとれます。
不登校情報センターのサイトへのアクセス数は毎日3000名くらいです。このレベルをさらに上げることが、これらの“仕事づくり”をめざす人への応援効果を高めます。そこでサイト全体の充実を不断に考えています(この部分は省略します)。
居場所ワークの特色は、居場所としての不登校情報センターの運営費を得ることと、参加する人の個人的な収入方法を連動させる点です。具体例を見てわかると思いますが、こういう形の引きこもりからの社会参加を進めているところは他に知りません。学校(職業訓練)型や福祉(社会保障)型に対して、私は自営(仕事づくり)型と理解しています。自分を生かす仕事づくりですが、これは独特な方法であり、これまではアピールするのをためらってきました。
しかも、現状は個人が収入を得る方法といってもこれから手掛けるもので、収入といってもわずかなレベルです。いきおい引きこもりからの自立の大部分は“戦場”ともいえる就職活動に向かいます。だがその結果は楽観できません。
いったん働きだしたのに、続かずに引きこもり生活の戻る人もいます。生きづらいままの生活に耐えている人もいます。就職型でなく個人が独自に収入を得る方法が願うのはこのような実例を多く見てきたからです。
その社会に就職(派遣やパート)やアルバイトなどで得た体験談を交流しあって互いに対応策を考えています。ときおり親の会などで参考意見として話し、非公式に集まり交流します。顔見知りになったとはいえ互いになじめない状態もあります。それでも苦楽を共にしてきた互いの経験が役立つ関係者です。
社会の変動は大きく、この数年は社会の側が引きこもりに近づいているみたいです。この仕事づくりタイプの活動をためらわずにアピールする時期がきたのです。似ているようでそれぞれ異なるまだら模様の体験者のつながりを生かして、不登校情報センターという居場所を社会に通用する方法を獲得する実地の試行錯誤の場にしたいわけです。これが居場所ワークの新しい形です。