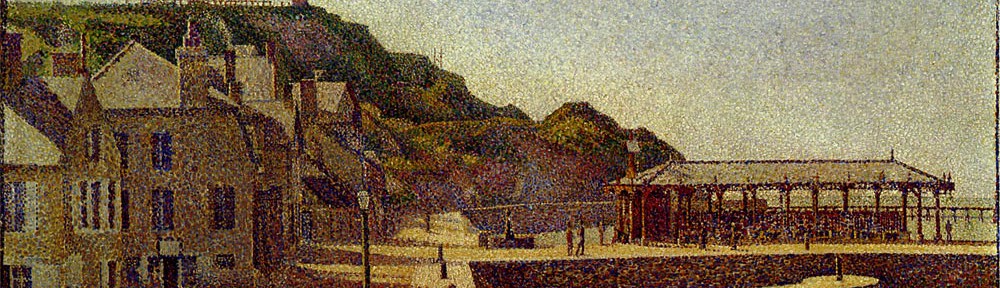会報」『ポラリス通信』9月号(32号)を編集・作成しました。
内容は、
連載「メンタルフレンド・力」の第6回/藤原宏美
エッセイ「引きこもりの親の会の最近の様子」/松田武己
イベントのお知らせ/
「バイトなどで働いてみた職場の事情と人間関係」(9月20日)
「みんなのパステルアート教室」(9月12日)
未来マップ「中高受験相談会」(9月6日)
「亀戸で不登校の進路相談会」(9月21日)
毎月の通常の相談・説明会日程などのお知らせ
明日30日には発送します。
月別アーカイブ: 2015年8月
「通所先としての不登校情報センター」の小冊子
先ごろ、40代の引きこもり状態の方を訪ねました。その人は出版物の編集経験があり、私の方から要望して来てほしいと思いました。
また訪ねようと思っているのですが、説明のために「通所先としての不登校情報センター」という小冊子(A4版6ページ)をまとめました。
引きこもり経験者の作業のある居場所の自己紹介です。当事者がどういう形で通所できるのかを紹介します。
(1)事務作業グループ
(2)情報サイト(ホームページ)制作
(3)大人の引きこもりを考える会
(付録)事務作業とホームページ制作の作業マニュアル
初めてまとめたもので十分とは言えませんが、活用しながら改定していくつもりです。
関心のある方(親を含む)にはお送りします。
講演と対応策「引きこもりから仕事についた人との交流会」
30代以上の長期の引きこもりを持つ家族が、心の問題レベルを超えて、経験した当事者の話を聞くなかで社会につながる手掛かりや方法を具体化する場です。
①、当事者に具体的につながる方法は3つあります。
*家族を介して当事者に訪問サポートでつながる。
*外出同行支援により当事者が就労・福祉・居場所につながる。
*当事者が不登校情報センターの居場所ワークにつながる。
②、参加を呼びかける対象者は30代以上の引きこもりのいる家族と当事者。予約制で20名。
③、内容の前半は取り組みの方法と体験報告。
*不登校情報センターの居場所ワーク=松田武己(理事長)
*訪問サポート活動の様子=藤原宏美(訪問サポート代表)
*体験報告者は、派遣会社の利用、清掃業界の事情、介護福祉の現場、郵便業務の体験、メカニック分野の仕事、女性の職場体験などを話せる人達と調整中(3人ぐらいが発表)。
内容の後半は、質疑応答、体験者等を囲む交流会、個別の対応策相談。
④、日時:9月20日(日曜日)午後1時から2時30分までは報告と発表。そのあと交流会と個別の対応策相談を最長9時まで。
⑤、場所:不登校情報センター=東京都江戸川区平井3-23-5-101の民家=小さな事務所(JR総武線平井駅南口5分)。
⑦、参加費:1人3000円(当事者は無料)。
⑧、主催・申込先:不登校情報センター(TEL03-5875-3730、FAX03-5875-3731、メールopen@futoko.info)、訪問サポートのトカネット(090-4953-6033)。
引きこもりの親の会の最近の状況と役割
不登校情報センターの親の会が始まったのは、2001年5月です。以後毎月欠かさずに開いていますので、累計170回以上になります。14年の間には大きな変化もあり、親の会の名称も2度変わりました。2012年5月からは「大人の引きこもりを考える教室」と称しています。それ以降の運営の基本形は同じですが、3年以上の期間のなかで少し変化もあります。最近数か月の様子を報告します。
定例会は毎月第2日曜日の午後1時~3時までの2時間です。
毎回の参加者数は10名から15名ぐらいが多いです。そのうち当事者(引きこもりの経験者)が数名参加するのが特色の1つです。
司会運営は私がします。会合の時間が2時間(30分くらい延長することもあります)、発言を希望しない親以外は全員から発言してもらいますので、1人当たり10~15分程度で近況を話してもらい対応方法を含む意見交換になります。
これを参加者が全員で聞きます。他の人の話しを聞きながら自分と子どもの場合を考えるのです。これらを聞くのに重点のある参加者もいます。
5人から10人が話しますので、短時間に収めるにはあまり脱線はしないような司会運営が必要になります。
かなり以前には数十人の親が参加した時期もありました。当時は状態の理解や感情面を共有することはできましたが、対応策を具体化する点が弱かったと思います。いまの内容を維持するには現状程度の参加者数がいいと思います。
参加する常連の親から聞くことは、子どもの様子がある程度わかるので、一通りの状況報告と意見交換は短時間で終わります。
初めて参加した人などは、状況報告や意見交換が長くなりやすいです。初参加者が多いと常連参加者の発言時間がとれないこともあります。
会の終了は3時過ぎなので(3時半を過ぎることはあまりありません)、その後、当事者を交えてのフリートークになります。隣り合わせの人や、当事者の誰かを囲んで話すなど、あちこちで会話が広がります。この時間帯は参加者の都合でいつ帰ってもいいわけです。それでも時には7時とか、8時過ぎまで続くこともあります。公式の親の会よりもこちらに関心・期待を持つ人もいると思います。かつての親の会にあった雰囲気がここにあり、しかも当事者が混じっている分いい形ができていると思います。
意見交流の内容面では、子どもが示すちょっとした動きや言葉をどう理解したらいいのか、親としてどう対応したらいいのか、外出の手掛かり、人とつながる手がかり…などをはじめいろいろな問題がでます。これらは参加している当事者からの体験したことを答えてもらうとわかりやすくなります。彼ら彼女らのことばは飾りがなく真情があふれているので納得しやすいのです。
時には年金の支払い、遺産相続、親族の関係などにもテーマが広がり…葬儀のし方を話したこともあります。これらも当事者の関心があり貴重な参考意見です。最近よく出るのは生活困窮者対策の福祉制度です。
そういう中でとりわけ関心が高いのは当事者がどうして引きこもりから抜け出したのか、動く気持ちになったかを聞くことです。アルバイトを始めた、派遣会社に登録した、仕事についた話にはよく耳を傾けています。当事者の体験談は断片的なことでも聞き逃さないみたいです。
当事者の話しで多いのは対人関係やコミュニケーション、職場での動き方などです。ここに表われる引きこもり経験者の話しは私にとっても貴重な情報源であり、引きこもりの心理やふるまいを理解する機会になります。
親の会の役割は親にとって有効であるばかりでなく、参加する当事者にとっても有効です。自分の体験したことを相対化する、出席者から質問されたことに答える形でことばにできるのです。そのことは自分が経験したことの理解を進めます。その意味では引きこもり経験者も親の会に参加するといいと思います。
親の会は引きこもりの理解、とりわけわが子との関係を改善するためのものです。私が意識するのはその理解を家族以外の他者とどう結びつけていくのかです。不登校情報センターには作業をする居場所ができています。ここにつなぐ方法が1つです。しかし簡単ではありません。この部分は「居場所ワーク」の項目で別に書きます。
その前に、家にいる引きこもる当事者と接触しなくてはなりません。自ら訪問を考えますが、無造作に訪ねても顔を合わせられません。そのための段取り、“作戦”が必要です。この部分は「訪問サポート」と「同行サポート」(5月2日「当事者に同行するオーダーメイドの取り組み」)の項目で別に書きます。
〔これは「かつしか子ども・若者応援ネットワーク」でまとめる報告書に提出する文書の下書きになります〕
沖縄のフレンズアブロードと珊瑚舎スコーレ
沖縄の高卒チャレンジ校フレンズアブロードから学校案内パンフが届きました。アメリカフロリダ州の私立アメリカンハイスクールアカデミー日本校であり、不登校情報センターの分類では、「留学・海外交流支援機関」になります。
9月6日の足立区の進路相談会「未来マップ」などの場でこの案内パンフを展示・配布します。
そのパンフをくるんでいたのが沖縄の新聞「琉球新報」8月14日号です。教育欄にフリースクール・珊瑚舎スコーレの記事を見つけました。珊瑚舎スコーレには中等部・高等部と夜間中学があり、その学習発表会の内容が記事になっています。9月には初等部を開設するようです。
[http://www.futoko.info/…/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%…](フレンズアブロード)
[http://www.futoko.info/…/%E7%8F%8A%E7%91%9A%E8%88%8E_%E3%82…](珊瑚舎スコーレ)
30代、40代の引きこもりへの訪問に手ごたえ
7月の引きこもり教室に初参加の方が数名いました。そのあと個別の相談を呼びかけましたが応える人がいませんでした。8月の教室は同じことを繰り返さないように、終了後2名の方に訪問する約束をしました。
その日に訪問したのは、独り暮らしをしている30代後半の男性Aさんです。同行したお母さんと一緒に会うことができました。3時間その息子さんからポツポツと話しを聞くことができました。次回訪ねるのは30日です。18日になってお母さんが1人で訪ねて行き短時間顔を合せました。髪を短く切っていたそうです。彼のなかに何かが生まれている気がします。
昨日17日は40代の男性Bさん宅への訪問です。お母さんは隣の部屋に移動していただき2人で1時間ほど話しました。自分からは話しませんが、私の質問には静かに答えます。不登校情報センターに来てホームページ制作を手伝ってほしいと頼みました。はっきりした返事はもらえませんが、訪問を繰り返すと動き出せそうです。
17日には、以前から訪問している30代の男性Cさんのところにも行きました。父と2人暮らしですが本人が1人いました。この人には自治体の福祉部に一緒に行く方向で動いていけそうです。
さらに20代の男性Dさんは8月から私の“定期的な個人授業”を始めました。夕方からの2時間です。文書入力をはさんでいくつかの取り組みを続ける予定です。
8月になってめざした方向はいい感じで進んでいます。紹介した4人以外も含めて、引きこもっている当事者の様子はさまざまですが、それに対応する型がそろった感じがします。
基盤として不登校情報センターに事務作業グループとホームページ制作という場ができ、訪問サポートの態勢があるので引き継いでいけます。そういう見込みがあるのでも引きこもっている人ができそうなことをスムーズに提案できます。
生活困窮者支援制度は、4月にできたばかりで未知数ですが、これを有効に使うのも手掛かりになります。
9月21日の亀戸で不登校の進路相談会
9月21日(月曜・祝日)に進路相談会を行ないます。
会場はJR総武線・亀戸駅近くの「カメリアプラザ(江東区亀戸文化センター)」6F・第2会議室。
時間は13時30~16時30分。
内容は、
①講演「不登校からの高校進学と中退からの再入学、転編入の仕方」(質疑あり)。
②学校案内書の展示と配布(不登校・中退者を受け入れる高校などの学校パンフ30校以上)。案内書を集めるだけの参加もOKです。
③個別相談(主に保護者の相談。進路だけではなく不登校の相談、対人関係、学習の遅れなどいろいろなことを相談します。生徒と一緒に相談することも可能です)。
参加費は無料。
定員は20名、なるべく予約参加をしてください。
主催・連絡先は不登校情報センター(TEL03-5875-3730、FAX03-3875-3731、メールopen@futoko.info)。
発達障害者のための教室・施設のページを準備
「発達障害生の教室・施設」の情報提供ページをつくるために、情報集めのためのフォーマット用紙を作成しました。
試作品とし、すでに情報提供をしていただいている5つの教室に送りました。現在、紹介している情報をこの試作品用紙に書きなおす形で書き直していただくためです。
興学社高等学院(千葉県松戸市)、発達支援教室ホーミーズ(東京都中野区)、工芸技能学院(東京都日野市)、太陽の村(神奈川県相模原市)、NPO法人発達わんぱく会(千葉県浦安市)です。
この回答を見て、フォーマットの正式版をつくり、一斉に送る予定です。
これまで迷っていたのは、障害者のための特別支援学校・養護学校のなかに含めるかどうかでした。特別支援学校・養護学校にも該当するところはありますが、そういう視点では探さないのが大勢と思えるからです。また(学校だけではなく)施設を加えることにも意味があると思えます。
関心のある人のご意見をお聞かせください。
閉校や活動停止の施設を「調査リスト」にまとめる
不登校や引きこもりに対応する学校・支援団体の動きにもそれなりの興亡があります。
事務作業グループでは、対応している学校・支援団体を探し出して、情報提供の依頼を続けています。その結果、この1年間で300か所以上がこのサイトに加わりました。
他方、たとえば今年の3月末に渋谷高等学院が閉校になりました。他にも活動停止や業種の変更もあります。…
事務作業グループの新しい取り組みとして、活動停止などのところを明瞭にする作業に取り組んでいます。活動していた学校や支援団体がわからなくなると戸惑う人も少なからずいるからです。
そこで不登校情報センターのサイトで紹介している学校・支援団体のうち、連絡が取れなくなっているところを事務作業グループで調べることにしました。
調査の結果、いろいろなことがわかりましたが、その団体独自のHPを持たないところを「活動状況の調査リスト」(故障者リスト)にまとめました。独自のHPを持たないことと活動の停止を同一に扱うのは本意ではありませんが、郵送などによっても届かないことがあると、他に判断材料がありません。
1年程度はこの「活動状況の調査リスト」に表示し、その後再度調べて確認できないときは削除します。今回このリストに掲載になったのは32件ですが、うち2件は調査で転居先が確認できました。リストに回さないで情報の更新依頼できるところは23件になります。
今回のこの方針は、紹介情報の一層の信頼度を高めます。また不登校・ひきこもりに対応する学校・支援団体の動向を把握するうえでも有効なものになります。これから調査する対象の学校・支援団体などはなお100か所以上はあります。
[http://www.futoko.info/…/%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%…]
8月9日と16日にSくんのDJ講座
SくんがひさしぶりにDJ講座を開きます。
8月9日(日)は、大人の引きこもりを考える教室のあと、4時前後からです。
その次の日曜日、8月16日もまた4時ころからです。
関心のある方はどうぞ。