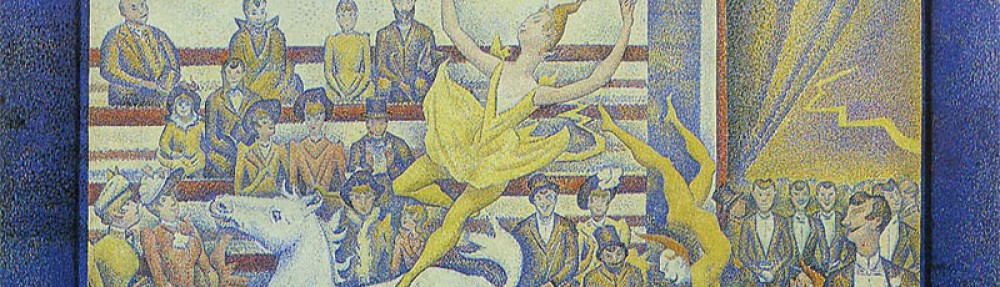最近の驚いた(驚かされた)話です。
40代の対人不安のある女性です。かなり離れた地域で開かれた引きこもり関係の講演会に参加しました。100名を超える出席者ですが顔を知る人はいないようです。会の終わりに「質問は3名まで」と言われ、2名の質問を終わったところで3人目の手が挙がりません。思わず自分で手を挙げていました。
さて質問となったのですが、あわあわして言いたいことがうまく言えません。
「どうしても人が怖いんです」「先生の所に診察に行けますか(講師は医師)」ということで終わったようです。
私にとってこれが驚いた話です。多数の出席者のいるところで挙手をして質問をする、驚くには十分な“事件”です。
会が終わった後、近くにいたおばさんから声をかけられて一緒に食事をすることになりました。質問に立ちあがったことで声をかけられたようです。その方には40歳近い娘さんがいて、いつのころからかまったく親子の会話ができなくなったと言います。
自分の話しをするつもりで、半分は娘さんの気持ちを考えてみようとしました。しかし、途中であきらめました。このおばさんは人が生きていくのに大事なことを一生懸命に話すのですが、相手の気持ちを聞いて理解しようとする姿勢はないのです。何を話しても「それはわかっている…」、「私もそういうことは経験した…」などというのですが、その部分にとどまって理解を深めるとか、話す相手の気持ちを考えるというのがありません。おばさんの大事だと思うことを手を変え品を変え話し続けていくのです。
自分の経験を話すとか、娘さんの気持ちを代弁しようという気持ちはたちまちうすれました。娘さんがこの親の前で何も話さなくなるのは当然だと納得しました。私にそういう体験を話してくれたわけです。
ときどき娘との会話ができない、という相談を受けます。この話しはそうなる原因、背景の一つがでています。親子関係というなかでも、母親と娘さんの関係に表われるのが特徴的です(一般論としては、父親との関係はそれ以前の気がします)。
困るのは話さなくなる娘さんは親や家族に対してだけではなく、誰に対しても話さなくなることが多いことです。“支援”としては、そうであっても話していくよりも、聞いていって理解しようとする姿勢がないと人と関わる糸口は見つからないのは確かです。