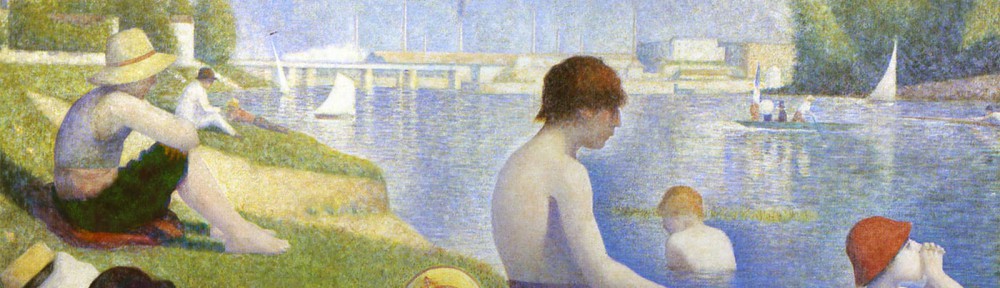書くことは苦ではありませんが、書く時間が取れないことが制約条件です。
机(パソコン)に向かってばかりでは姿勢に、眼と腰に悪いです。仕事としての取り組みや相談があり、外出も必要です。苦にならないとはいえ書くことばかりに集中できません。
不登校情報センターのサイト制作に関わらなくてはなりません。
そこでサイト以外のブログなどのSNSは省略型で行っています。
ブログは「引きこもり居場所だより」です。いろんなことはここに書きます。これをツイッターとFacebookに転載しており、だから省略型です。
ブログに書いたものはすべて自動的にツイッターに転載されます。
Facebookには、3つのページに分けて転載します。
Facebook内の「不登校情報センター」には、主に居場所の様子とサイト制作に関する記事を転載します。
「不登校・ひきこもりサポート相談室」が昨年秋にできました。相談員3名で、それぞれが記事を書くことになっています。ほとんど私の転載記事です。今後も変わらないかもしれません。
「松田武己」ページもあります。個人的な事情を転載しますが、他の2つのページが適当でないときはここに載せます。
月別アーカイブ: 2015年2月
アスペルガー気質の理解に異論あり
私が最近書いている感情・感覚の理解に「どうしてそんなことがわかるのですか」みたいなことを言われました。そこを少しばかり…。
私は自分でもアスペルガー気質を自覚するようになっています。
先年、ある学会が症状やとらえ方の変更により用語も自閉症スペクトラムになりましたので、アスペルガー気質ということば遣いもそのうち変えることになります。
それはともかく…。
アスペルガー障害は周囲の人の感情把握がうまくいかないことがある、と称されているものです。アスペルガー気質はそうなりやすい体質の性格的な面を指しています。ある程度は周囲の人の感情把握がうまくいかない理屈になります。
ですが、私の個人的な体験ではその部分は少し違うようにも思います。どう違うのかというと、周囲の人の感情をよく把握できることもあるのからです。いつもそうというのではありません。
私が引きこもりの経験者と関わる内に感じる、彼ら彼女らの感覚・感情を察知する経験は「周囲の人の感情把握がうまくいかない」だけでは説明できないからです。何しろ私は系統的に心理学などを学んだことはありません。ほとんどが自分の関わってきた人たちから直接に感じたことを自分なりに構造化してみたものです。心理学の予備知識から理解してきたとはとても言えないからです。
そこで持論として「アスペルガー気質は周囲の人の感情把握がよくわかるときとよくわからないときの両極に振れやすい」と考えることにしています。よくいうゼロヒャクの感情把握版です。どうでしょうか。
「働いた経験のない息子の相談」に二条淳也さんが回答
「30代後半の働いた経験のない息子の相談先」という質問があり、それに二条淳也さんが回答を寄せてくれました。
不登校情報センターのサイト内には「不登校・引きこもり質問コーナー」というページがあります。200項目ぐらいの質問があり、15人が回答しています。多くの項目に回答している人もいれば、1項目だけに回答している人もいます。質問も回答もオープンになっています(質問者は特定できません)。
回答を書いていない項目も数項目あります。質問を受けたときその場では回答をしているのですが、それをいつも文章化しているわけではないからです。今回の二条さんの回答もそういう項目に自分の経験から回答していただいたわけです。もちろんある質問に2人以上がそれぞれの回答をしているところもあります。
この「不登校・引きこもり質問コーナー」の骨格は2年前に制作しました。
質問項目、回答項目が中心ですが、検索できるように工夫しようとして途中で混雑しています。似たような質問もありグループ分けしようとして行き詰まっている様子があります。この質問コーナーだけでも独自の大きな(ポータル)サイトなので、継続的に整理整頓の担当者がほしいぐらいです。
なお、質問は受け付けています。回答も受け付けています。特に当事者からの経験に基づく回答は大歓迎です。
人と話をするのはカウンセリングみたいなもの
2月10日の「精神科の受診を続ける理由(わけ)」と同じ人から聞いたことです。
あえてカウンセラーでなくても、普通の人と話をするのも“カウンセリングみたいなもの”になるといいます。
どんな人との会話でもそうなるというのではありません。近所の好感のもてる八百屋さんとの話はそうはならないと断言していました。
しかし、歯医者に行ったときはそんな感じがしたといいます。そのために歯医者に通っていることもあるとか。この違いがどこにあるのかはよくわかりません。
どういうつもりで精神科に通院を続けているのかといえば「医師が私のこういう状態を少しずつわかるようになるのをお手伝いしている感じです。通院する主な理由というよりも、そういう面もあるのです」からです。それと“カウンセリングみたいなもの”とを重ねてみると何かわかりそうです。私が理解できることのちょっと先にある現象です。
それにこんなこともあります。
自宅にひきこもりほとんど外出しない人が先日から電話をしてくるようになりました。その人は誰とも話をしないでいると孤独感から怖くなるといいます。
また別の人ですが、人とじっくりと話しができた後はすっきり感があり元気が出るといいます。
この対極にいる2人の話しを総合すると、話をするのも“カウンセリングみたいなもの”になるのは本当なんです。どういう人とどういう形での話ができるかによって“カウンセリングみたいなもの”の様相が違ってくるのでしょう。これがさしあたりの結論です。
聴覚だけでなく皮膚からも音情報を集める感受性
引きこもりになる人は相当に感覚が鋭いと感じることは多いです。それにも個人差があり、どの部分がどうというのは一律ではありません。
嗅覚がいい人、味覚がいいと思える人、そして聴覚がいい人というように特徴というかズレがあります。
室内で話しているのですが、外の様子がよくわかるような人がいます。ほんとにわずかな音でも聞こえているのでしょう。
ある人と話しているときのことです。「何かいる」というのです。確かに耳では音は聞こえてはいないのに、何かの気配を感じました。振動を感じるといえばいいのでしょうか。音にすれば非常に低い音になるのでしょうが、通常の人の耳では拾えないようなにぶくて太い響きです。
これは耳ではなく、皮膚感覚または身体感覚でとらえていたように思います。
それ以降は、気をつけていると時たまそういうことがあります。
聴覚とは空気の振動を感覚器官がとらえることです。しかし、人の耳がとらえるのはある範囲の音の波長です。その範囲は人により多少の違いがあり、聴覚の優れている人はこの範囲が広いのでしょうか。しかし、それだけではないとこの時から考え始めました。
耳以外でとらえる空気の振動を皮膚感覚でとらえるとなると、これは皮膚にも聴覚に匹敵する役目があることになります。
ひきこもりの感覚の鋭いというのは皮膚感覚が鋭くて、周囲の音を皮膚からも集めているように思います。
このことを、私は傳田光洋『皮膚感覚と人間のこころ』(新潮選書、2013)を読む前に書いておくべきでした。この本ではそこを解き明かしています。自分も気づいていたというのは出し遅れ感はありますが…。
体毛の消失も同じ本で書かれています。私が「体毛の消失と感情表出の発達」を書いたのは2005年2月です(「五十田猛・論文とエッセイ」に掲載していますから見てください)。
マッサージの心へのを働きを実験科学の研究から紹介
以下は、ある本からの引用です。
「皮膚への刺戟による医療、例えば東洋医学における鍼灸もそうですが、マッサージの医学的効果についても、実験科学的な方法で研究が進んでいます。特にマッサージの施術は、現代医療では難治とされている疾患にも応用されています。……
子供の自閉症、多動性障害に対して、マッサージの施術がその症状を軽減させたという報告があります(Escalona A.2001.J Autism Dev Disord 31:513-6/Khilnani S.2003.
Adolescence 38:623-38)。
また思春期の攻撃的行動の抑制にも効果がありました(Diego MA.2002 Adolescence 37:
597-607)。
うつ状態の緩和、あるいはアルツハイマー病に対しては行動面での改善も報告されています(Hou WH.2010.J Clin Psychiatry 71:894-901/Rowe M.1999.J Geronol Nurs 25:22-34)。
その他、類似の報告は枚挙に暇がありません。
効果があることは確かなのですが、それらの効果のメカニズムについては完全には明らかになっていません。マッサージの施術によって交感神経系活性より副交感神経系活性が優位になるという報告はありますが(Diego MA.2009.Int J Neurosci 119:630-8)、皮膚表面への接触がどのように受容され、神経系に作用するかは、まだ不明です。」
これは傳田光洋『皮膚感覚と人間のこころ』(新潮選書、2013、110-111ページ)に紹介されていることです。皮膚感覚がこころにどれだけ影響するのかを多くの研究者の研究成果に基づいて展開しています。
私がこれまでに感じてきたいくつかのことにも直接に言及しています。
人間が体毛を消失してきたことは感覚や感情の役割を高めるのに関係していること(以前に書いたことがあります)、
皮膚は聴覚をもつのではないかということ(これは書いたことはありませんが、ある程度は確信していました)、
そのほか思いがけないことが研究され紹介されていて、この本は読みごたえがあります。
アンデパンダン展に行こうという人はいませんか
Sさんが作品を出展するということで美術展の招待券を送ってきました。
第68回日本アンデパンダン展、3月18日から30日まで(24日は休館)です。
会場は国立新美術館(地下鉄日比谷線「六本木」から5分)です。
招待券は数枚ありますので,必要な人には送ります。
3月26日(木)などに作品合評会があり、私は時間的な都合がつけば(他の予定が入らなければ)この日に行こうかと考えています。
主催は日本美術会、いろんなことは日本美術会のHPを見てください。
ひきこもり社会参加に精神保健福祉センターが関わる様子
今年に入りひきこもりからの社会参加を支援する団体機関の情報集めをしています。
その中でいくつかの動きがわかってきました。
県単位でこの動きを把握(または奨励)しているところがあります。その中心はバラバラなのですが、精神保健福祉センターが管轄する地域の対応機関・団体をまとめて紹介する例が複数県で確認できました。
そこで全国の精神保健福祉センター70か所に情報提供をお願いしました。
全国の精神保健福祉センターには2012年2月に「ひきこもりと精神保健福祉センター」という名目で情報提供をお願いし、25か所から回答をいただいています。その時に次ぐ依頼です。
今回お願いした内容は次の点です。
(1)対応する団体・機関の連絡先や取り組み状況をまとめ、広報する「ガイドマップ」を作成しているか。
(2)対応する団体・機関などの経験交流等の機会を持っているか(2013年4月以降)。
(3)精神保健福祉センターが直接に関わるひきこもり・ニートを含む若年無業者への取り組みはあるか。
(4)ある県においてひきこもり・ニートを含む若年無業者に関わる独自事業をはじめています。精神保健福祉センターの管轄自治体においてその種の事業や支援策をご存知ありませんか。
(5)自由意見、その他の動向がありましたらお聞かせください。
2月23日現在、8つの精神保健福祉センターから情報提供をいただいています。来月にはサイト上に掲載する予定です。
〔2月25日の追記〕 12府県市の精神保健福祉センターからの回答をいただきました。
社会参加や就業支援という面では、期待をするのが元もと窮屈な公共機関です。回答は「それにしては…」という感があります。
紹介する前に、2012年8月の「引きこもり・不登校・発達障害と周辺状況への対応」の掲載を大幅に整理し直しました。これにより今回の「ひきこもりの社会参加に関わる精神保健福祉センターの対応」の位置が理解しやすくなると思います。
息子の言い分を聞きました
「おやじが元気にしているかどうかを見るため」と称して息子31歳がとつぜん来ました。
生活のためにある仕事に就きながら、将来は好きなことで生活できる準備をしています。数年間でしばらくは何もしないでも生活できる貯金ができた。ある人から住み込みで暮らし集中的に取り組んでみたらという話があった。それに乗ろうと考えているがどう思うか。考えを聞きに来たわけです。
音楽と絵の両方をしているのですが、どちらかはまだ決めかねているようです。
少し前に「音楽は才能がない」と言っていましたが、おやじバンドのおじさんたちに重宝されて、その関係はいまも続いています。
絵の方はご存知のスタンプを作り提出しました。珍しいタイプの「No!」を表現する絵柄であり、“毒味”を含んだものです。40点が1単位なのですが、うち1点は「公序良俗に触れる惧れがある」という書きなおし指示があったといいます。包丁を持っていた絵のようです。これでいくぶんはスタンプの「No!」を表現する絵柄を思い浮かべることもできるでしょう。日本人は断るのに苦労していますから面白いと思うのですが、一線を超えた表現なんでしょう。
で、絵か音楽に集中して取り組んでみようというわけです。このまま1日に数時間自分の将来に向けて細々とやっていても、埋もれてしまうと考えたようです。
はじめは何を言い出すのかと聞いていましたが、聞くことが大事であって、こちらから言うことはありません。最後に「それは自分で決めることだ」で終わりました。
うまく行かなかったとしても、その時にはまた何とかなる。そういう“根拠のない楽観”がこういう選択を考える条件になると後になって気づきました。
不登校親の会の丁寧で的確でわかりやすい紹介例です
「京都不登校の子を持つ親の会」からの連絡により紹介情報を更新しました。
紹介内容が丁寧で的確でわかりやすいと思いました。
親の会とは何か。こう紹介されています。
親たちの居場所、安全基地であり、毎月の「例会は登校拒否や不登校になった子どもの親たちが安心して思いを話すことができる、他の人の経験談を聞くことができる、否定されず攻められず指導されずにゆったりと受けとめ合う交流のひと時です」
もう一つ「必要とする情報」として、「予約は当事者の保護者の方は不要ですが、初参加の場合は確認のために事前にお電話ください。
なお、各種の学校や事業所、団体等の宣伝・アピールはお断りしています。支援者や学生などの方は必ずお問い合わせください」