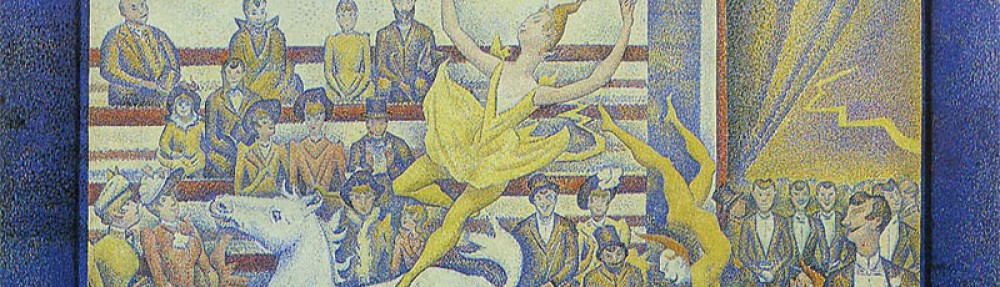私は台所周辺の板の間でときどき横になってしまいます。ぐっすりと眠ってしまうことも珍しくはないようですが、たぶん短時間です。
情報センターでのこの光景はそう珍しいことではありません。いつでも、どこでも寝られるというのは私の特技です。もっとも厳密な意味では「いつでも、どこでも」ではないのですが。
こう書くのは、眠れない人が多いからです。詳しく調べたことはありませんが、引きこもり経験者にはよく眠れない、寝つきが悪いという人はとても多いです。眠れないために睡眠薬や睡眠導入薬に頼る人が多いです。
私はなかば冗談ですが「薬物削減カウンセラー」になろうかと考えています。たぶん薬事法とか医療諸法に抵触しないと確信すればそうしたいと思います。薬物の服用は、短期的な効果を求めて長期的・基本的な目的を見失っていると思うからです。
この続きはまたの機会にして、睡眠の話に戻しましょう。
最近読んでいる本に『人間工学からの発想』(小原二郎、講談社ブルーバックス、1982年初版)があります。そのなかの1章に「寝具の人間工学」がありました。布団・ベッド、枕など寝具に関する面から睡眠を取り上げていて、医学的な面とは違う睡眠の見方を学べます。
そのなかに寝具の、特に敷き布団、ベッドの硬さについて書いてありました。適度の硬さが必要とあり、西式健康法の「平床硬枕」をその面から評価しています。私が板の間で眠れるのはその点から納得する面がありました。
引きこもり経験者の日常生活を見ると、薬物に頼ることだけではなく、他にもいくつか思うことがあります。自然な回復力を伸ばすのではなく、逆に免疫力を下げてしまうのではないかと思うことです。そのあたりをときどき書いてみましょう。