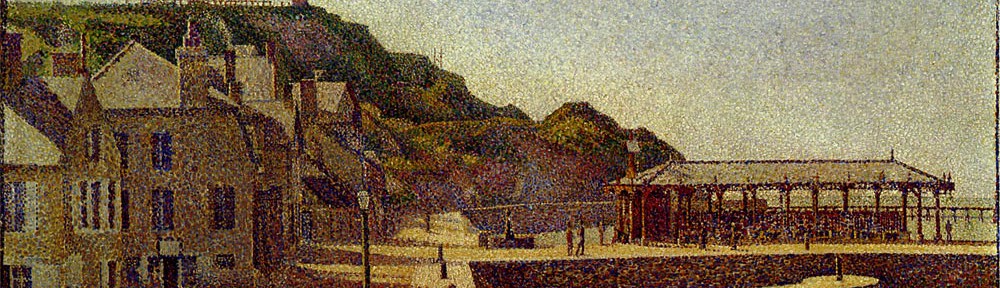滋賀県の保健所の対応を滋賀県精神保健福祉センターのガイドブックによる紹介情報の転載で紹介しました。
それを作成する過程でいくつかの傾向・動向を見ることができました。
滋賀県精神保健福祉センターとしてまとめた引きこもりに対応する県下の保健所の情報は大筋においては不登校情報センターとして把握し、紹介していこうとする内容と大差はないものと思います。
それでも細かく見るといくつかの重要点があります。
(1)一つは保健所への交通と、開所時間を明記していることです。地域の現実に根ざした活動をしている証拠です。
(2)滋賀県精神保健福祉センターとして把握ないしは推進しようとする活動を具体的な項目にしています。多くの保健所はそれへの対応は「なし」または無回答ですが方向を示しています。その項目には私たちが実態的には追求しているものもありますし、見えない部分も見せてくれます。たとえば草津保健所の回答です。調査項目に該当する取り組みがなくても「無」と答えたので、このガイドブックはその16項目を全部掲載したのです。
「①面接相談:予約制。主に保健師が対応。②カウンセリング:無。③訪問:面接相談において必要と判断した場合は、保健師による家庭訪問を実施。④居場所提供:無。⑤共同生活:無。⑥グループ活動:無。⑦作業:無。⑧電話相談:平日(祝祭日を除く)9時~16時。⑨外出付き添い:無。⑩社会資源利用:必要に応じて同行。⑪職場体験:必要に応じて同行。⑫職場訪問:必要に応じて同行。⑬インターネット相談:無。⑭親の会・家族会:無。⑮ニュースレター発行:無。⑯イベント開催:無。」
相談とカウンセリングを分けています(不登校情報センターも分けています)。訪問、居場所提供、グループ活動、作業、親の会などは不登校情報センターでは実施しているものです。
社会資源利用というのに「必要に応じて同行」と回答しています。これは居場所コーディネーターを試みるSさんの取り組みを思い起こさせてくれます。
インターネット相談は「ネット相談室」として立ち上げたものです。
しかし、不登校情報センターの取り組みには、共同生活、職場体験、職場見学は例外として行なったことがありますが通常はありません。
これら全体から引きこもり支援の基礎的なものが浮かんでくるように思います。仕事づくりや創作活動支援、ネットショップ、学習支援などは保健所の範囲ではないのですがこれらを含めるとさらに全体像が出てきます。
(3)もう一つ重要なのは、保健師が実態的に引きこもりの判断をしつつあることです。当事者・家族と面談をし、心理士のカウンセリングにつなげるのか、精神科医の精神保健福祉相談につなげるのかの判断は保健師が担当していると読み取れるからです。
これは私が提唱している引きこもりの判断は医師だけにしないで、実際に関わっている人たちにも開放するという方向を一致します。それは現実的な背景を持っているばかりではなく、すでに部分的に始まっていることを教えてくれました。
滋賀県以外の保健師の状態をみると、滋賀県における保健師の状態とは矛盾していないことが確認できます。それだけに滋賀県精神保健福祉センターの調査結果は優れているのです。それは調査項目によるのか保健所の回答者がそうしたのかの判別はできないにしても結果は際立っています。