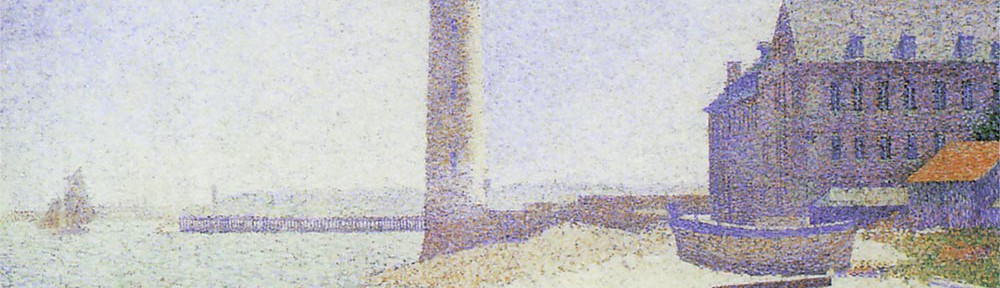碌さんが出展する作品は当日持参することになりました。
「どんな作品なのか口で言ってみて」と聞いてみると、
「とっても細かい……だから作品は大きくない」ということです。
前回の作品を知ればその意味は少し想像できます。
前回の出展作への感想にこんなのがありました。
「切り絵の額と絵が調和していてとてもすてきだと思いました。額の細い作業(デザインと切ること)はとても時間のかかることですが、すばらしいです。絵はピンクと黒の色調が気持ちよくて、あたたかい気持ちになりました」。
前回の作品でも相当に細かい作業を重ねたことが見て取れます。
それよりもさらに細かな作業をしているのでしょう。
前回作は6点あり、全体の構造、色使いと色構成の妙、これが見るものをひきつけます。
それを知るだけに“碌さん、また何かやってるな”と思わずにはおれないものです。
あと3日に迫りました。新作を出展できるメドが立ったのでしょう。