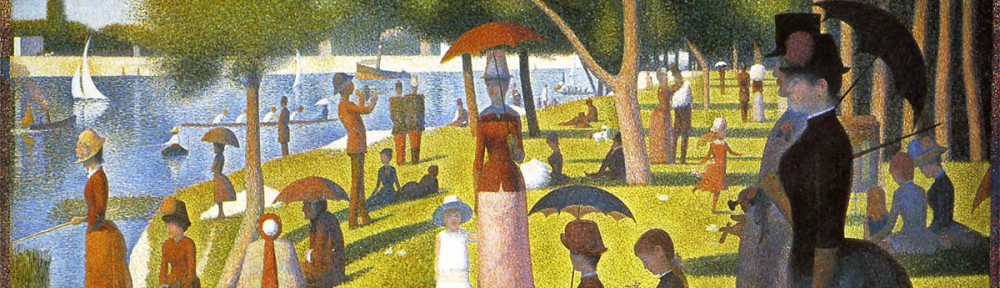創作活動を勧める意味を会報で「みか」さんが説明してくれました。私の思っていることを、私以上に行き届いた形で、わかりやすく説明しました。それで私は別の面での創作活動を勧める意味を書こうと思いました。
イラストをよく描く人がいました。そのお母さんが叱っている(?)ようなのです。「こんなことが上手くなっても何にもならない。経理学校にでも行った方がよっぽどいい…」という主旨でした。
その言葉の強さにイラスト好きのその人ばかりか、離れたところで見ていた私も何も言えません。今に思うと実に残念で情けない結果です。
人には向き不向きがあり好き嫌いがあります。不向きなどにより社会で生きていくのに差し障りがあるのであれば最低限の位置をめざすことになります。しかし多くは自分の好きなこと、自分に向いていることに取りくめば、スムーズに前進できますし、達成も多いのです。
私は、いつかわからない時期から表現活動を勧めるようになっていました(向いているかどうかは別です)。若い時代に本の編集者になったのは偶然でしたが、そこで思った以上のことを学び、身につけました。ひきこもり経験者と関わるなかでも、文章を書き絵に描くこと、創作を当然のように勧めてきました。
「ニート・ひきこもり支援」として社会生活、経済生活のできる力をめざすプログラムが大事にされるのを否定するつもりはありません。しかし、この方法で現実に生まれていることは次のように表われています。
(1) 当事者の心身状態でこの形に合う人が対象になり、全体への対応にはなりません。それ以前の課題がある人は少なくないのです。
(2)対応内容が就業支援中心にならざるを得ません。これが現状のひきこもり支援が就業支援に偏っているといわれる理由です。
(3)当事者の提起するものを受けとめられず、当事者を社会への適応・同化を促す対応になります。上記紹介のイラスト愛好者に経理学校を勧めた人がしていることがこれです。
私はそういう就業に固定した取り組みをするのは向いていないこともあって、別の道を進んだことになります。それが創作活動を勧める道です。
一般には、中心的方法以外の多様な道を肯定してよい、と思います。人は多様なわけで、好都合な道があればそこから目的に近づくことは可能です。
2023年に太田勝己作品の展示企画が提案されました。Tokyo-U・クラブというグループの提案で、企画が具体化し進んでいくなかで、そのテーマが「ひきこもりと表現」になりました。Tokyo-U・クラブ会長のKさんが提案したものです。企画の準備過程で十分に練られた結果とはいえませんが、私はかなり斬新さを感じるテーマに思えました。
考えるにひきこもりを続けるなかで失われる、むしろ育たないのは表現ではないでしょうか。自分の気持ちをどう表わすのか、思いや考えを周囲の人に伝えるにはどうするのか、それが表現です。ひきこもり生活では、ときには家族とさえも話すことはありません。表現力を失うのではなく育つ環境がないのです。ネットやSNSがそれを補充する面はありますが、生の社会的様子を知らないとうまくいかないのではないか。「表現」という提示はそれを考えさせてくれました。
表現と創作活動は同じではありません。表現が日常に求められるとすれば創作は自分の中の目的の意図性、構想や論理、感情の主体性が求められるという意味で、表現と創作には連続性と重複性があります。
結局私は、自分のできそうな分野で(必ずしも得意分野とはいえませんが)周囲に集まってきたひきこもり経験者たちに、創作活動を勧めることで、自分を表現することを勧めてきたことになりそうです。
ネットの普及によりあたり前に、ある情報、特定の事柄に関する知識を得られるようになっています。私はここに危険性を感じています。AIが活用されるようになって、さらにその感を強くします。自分の内側からのものを通さない多くの知識や情報を得られるようになり、それでわかった気になるのです。自分に受けとめる実感がなく、自分の感覚や経験を通さないで分かったつもりになるのです。それは何かを失われる感じがします。表現は、創作活動は自分の内側から出るものです。自分の感覚、自分の経験を通して、「正しい」とされるものとの整合性が確認される必要があると信じます。自分の感覚をもっとも大事にしたいのです。