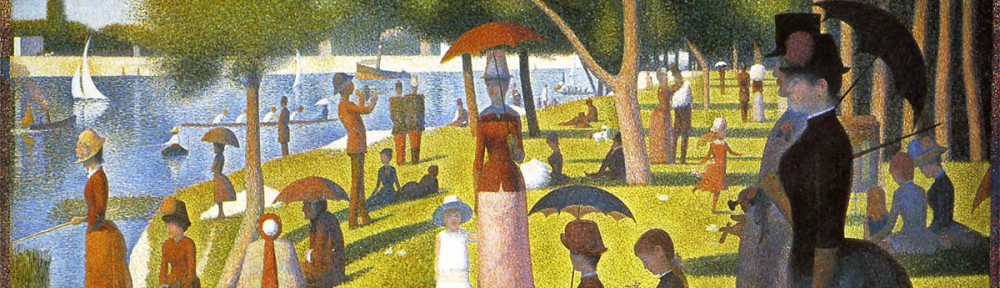会報『ひきこもり周辺だより』(2025年3月号)掲載
3年ほど前からひきこもりへの対応を個人の精神心理面から見ていく視点から社会的背景から見ていく視点に移しました。社会的背景とは1960年代の高度経済成長期に家族関係が大きく変わり、その変化を感覚よく察知した若い世代に社会的なひきこもりが生まれてきたと理解できるようになりました。
私と関わった不登校やひきこもりの人が生まれたのは主に1970年以降です。このような変化は個人差がありますからいっぺんに全部が変わるではなく、若い世代の感受性の豊かな人から変わるのです。
こうして私は、ひきこもりの背景には家族状態の変化があるとみて、それを調べ始めました。歴史はこれまでの家族状態では継続できないときに、ゆっくりと徐々に変わると示しています。その動きの原動力は(少なくとも日本の今回の場合)、子育てなどの家族内ケアが持続的にできるかどうかにかかっていると見えます。
家族にはいくつかの役割があります。毎日の生活を続ける衣食住などのルーチン作業と子育てに代表される家族内ケアがその2つの部分です。これに関わる多くのエッセイを書いてきたのですが、小難しい読み物になり敬遠されると予感して、会報に掲載するのはごく控えめでした。
もっと分かりやすく、日常生活に関係するところを会報の先月2月号に載せました。家事労働の現状を表わす図表などです。会員・読者にはこれなら比較的に近づきやすいと考えたからです。ある人が自分のばあいを手紙で知らせてくれました。この手の話ならみなさんにも話しやすいので、親の会などでも話題にできそうです。この人の了解をいただければ、会報に掲載しみなさんの状況を話す糸口にしたいと思います。
それにしても人間の生活において家事は軽視されています。少なくとも収入を得られる仕事と比べて評価されていません。大事だといっても、言葉以上に大事さを表わす基準がありません。どうすればいいのか。あれこれ考えていたところ、世界には既にそう考える人はいました。どうやら国連に持ち込まれて専門的に研究されているようです。
今回は、そういう事情を調べたものを紹介します。実際には多くの周辺分野がありますが、今回はその1つとみてください。
▽家事労働を金額評価する基準作成の動き
私は家事労働に目を向けました。その労働が数値表示、特に金銭評価されていないために軽視される位置におかれているからです。
(1)それは、人類の発生以来(発生以前から)行なわれていた生存のための活動、生理的活動の継続を示しているとの認識に至りました。
(2)家事労働に限らず、このように数値表示されない活動は他にもいくつかあります。現代における代表的なものは、ボランティア活動です。ほかにも物々交換、自家消費生産もそうでしょう。有償・無償の境界ははっきりしませんが、入会権など共有地における労働や、細かくいえば家事と分離されない家業(商店・町工場など)の家族労働などが入ります。
こうした家事労働とそれに似た傾向にある数値表示されない、非評価労働をどう評価するのかを考えました。暫定的な結論は2つです。
1つは、家事労働のそれぞれに匹敵する市場換算に表出された労働(これは職種に当たる)に比定して、その対応する家事労働を労働評価していく方法。
もう1つは、家事労働の労働時間を、金銭換算しないで労働時間(望ましいのは社会的平均的な労働時間)を評価数値として表示することです。
このうち家事労働に対応する職種の賃金水準をもって家事労働を評価する試みはすでに始まっていることを知りました。それを紹介する論文「SNAにおける無償労働の貨幣評価と家計勘定」(佐藤勢津子/専修大学大学院,作間逸雄/専修大学経済学部)を参照に説明します。
SNAとはSystem of National Accounts(国民経済計算体系)という国連の機関です。そのサテライト作業の1つに無償労働の貨幣評価は取り組まれました。「1995年、北京女性会議は、その行動綱領のなかに、無償労働を貨幣評価し、中枢国民勘定ではなく、サテライト勘定にそれを反映させる方法を研究すべき」としています。30年ほど前にここまで話は進んでいたのです。
日本では1996年旧経済企画庁経済研究所は無償労働の貨幣評価を研究し、その推計結果を1997年に公表しました。
*経済企画庁は日本の国内総生産(GDP)をまとめる政府担当機関であり、これは省庁改編後には内閣府にひきつがれています。
上にいう中枢国民勘定とはGDPを指しています。SNAは、世界各国のGDP算出の基準も決める国連の機関です。その北京女性会議は第4回世界女性会議です。
日本の家事労働評価は、1997年からこの論文発表の2013年までに4回行なわれ、その都度いくつか改訂され、担当部署も交代しています。
評価には3つの方式があります。算出に用いる基礎データは、時間使用調査による行動カテゴリー別時間データと男女別、年齢別、職種別賃金データを使い、それには総務省統計局「社会生活基本調査、厚生労働省賃金構造基本調査(賃金センサス)」が主に用いられています。
方式が3つに分かれるのは、行動カテゴリーを予め定められている(プリコード方式)、記入者が自分で何をしていたかを自由に記入できる(アフターコード方式)、そして第三者基準(委任可能性基準)です。いずれも行動種類の中で無償労働に対応するカテゴリーを取り上げてその行動時間を賃金データで評価するものです。
家事労働を職種に当てはめる代替費用法を2009年公表の対応職種でみると次のようになります。
炊事→調理師、調理師見習
掃除→ビル清掃員
洗濯→洗濯工
縫物・編物→ミシン縫製工、洋裁工、洋服工
家事雑事→用務員
買物→用務員
育児→保育士
介護・看護→看護補助者、ホームヘルパー
「家庭内サービスを代替するサービスを生産する産業の現業職種は一般に低賃金である」(p9)とされています。これらを「家事的労働」と呼ぶ人もいるようです。上の家事のうち育児と介護・看護が私の分類する「家族内ケア」になります。
これら右側に表示されている職種の〈時間給〉がどれくらいかは調べていませんが、
‘’納得のいかない‘’事情説明を実際にされているみなさんにそれぞれ教えていただきたいわけです。
1997年の経済企画庁の推計結果をこの論文筆者は次のように紹介しています。
「基礎統計である時間使用の制約は厳しく、各国の先行事例と比べて過小評価にならざるをえなかった…先進諸国の無償労働者の貨幣評価額は、GDPのおよそ6割であり、わが国の無償労働の貨幣評価額(20%台)との差を統計上の問題として説明することは不可能と思われる」(p5)。
著者は遠慮がちに言っていますが、日本の家事労働評価は先進諸国と比べても半分以下にしか評価していないとあきれているのです。お分かりでしょうか?
その後の年度の家事労働の評価方式がどのように変化したのかはまだ調べていません。いずれにしても不十分であり、大いに改善の余地はあると思います。そう判断しますが、しかし、家事労働を金銭評価する一つの土台ができていたことは大きな発見です。
それにしても、この質量の評価レベルをそのまま家族の世代継承機能を有償換算された表現とみるには、あまりにも軽率であり、事の重要性と結びついていない感じがします。機会があればこの評価内容に言及したいと思います。
●これを「家族と家事労働」勉強会にしたいと希望します。賛同者はいませんでしょうか。論文が多くあり、分担をして読みたいと思います。