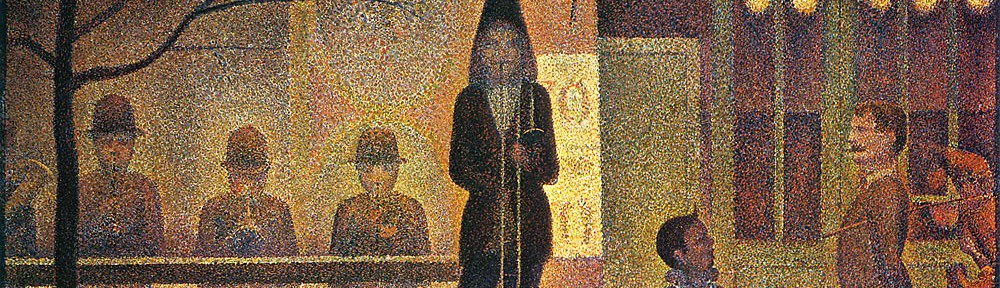松田武己の子ども時代を「アスペルガー気質の少年時代」としてまとめることにしました。いろいろな生活場面に子ども時代の私が行ったことを、あれこれ書いてきたので、それを 1つにまとめようというわけです。
思いついたのは「文学フリマ・東京」に出展する目標で、これまでいただいた数人の手記などを手作り本にする作業を進めていると途中です。①小林剛『ひきこもり模索日記』は不登校からひきこもりの時期を、②逸見ゆたか『精神的ひきこもり脱出記』は私より10年以上先輩の体験を、③高村ぴの『アルバイト体験記/対人恐怖との葛藤』は書名そのまま、④ナガエ『私の物語』は子どもの虐待と解離性人格障害を——これらは新しく追加して手作り本にするために元の原稿を読み返すなかで確認したことです。
そういえば中崎シホ『喪失宇宙からの手紙』はある文学会の公募に提出したので、結果発表は5月ですが、応募したのは昨年12月のことです。この作品が事実上はじめの動きかもしれません。
不登校情報センター(あゆみ書店)の、そこに関わる人たちの特徴的な傾向が、ここにそれぞれが表現できていると思えたからです。不登校情報センターに関わる人には、それぞれ特徴的な様子を表現する人、特別の体験をする人がいます。それらを手作り本として実現すれば、そこが明確に表われるのです。
それらに関わるなかで、私自身のアスペルガー気質の様子をまとめようと思い至ったのです。アスペルガー障害は、最近は自閉症スペクトラムという枠に収められて診断されますが、むしろアスペルガーの用語を入れる方がそのある傾向をクリアーに表現すると思えますので、そして私のばあいは比較的軽度(異論のあることは認めますが、社会生活に大きな影響は少ないと勝手に判断して“軽症”とします)ですが、発表することにしました。
さて『アスペルガー気質の少年時代』は、2007年以降に私の子ども時代を思い出して書いたものです。私がそれを自覚したのは不登校情報センター内で行った2007年秋の、心理カウンセラーKさんの「アスペルガー障害の学習会」でした。
Kさんは、不登校情報センターに来て通所するひきこもりなどの経験者、訪問サポートする学生らと相談を続けていました。定期的に学習会も開いていたのですが、私はこの学習会で初めてそのレクチャーを聞いたのです。
その話を聞きながら、それはまるで私の子ども時代の様子を聞く思いでした。「そうか、自分はアスペルガー的傾向の強い人間だったんだ」と悟りました。62歳のときです。もはや何かをとり戻すことはほとんどできない年齢です。しかし、何かホッとしたというか落ちついた安心した気持ちになったことを覚えています。
これをKさんに伝えると「ペンの持ち方とか、いろんなことでそう思っていましたよ」という主旨の答えがありました。お見通しでもあったわけです。私がここでアスペルガー障害と自認するのではなく「~気質」と表現するのは程度が軽いということと、Kさんがそのときは「~気質」と言ったことによります。
《そこを起点にしてこれまでを振り返ってみると了解できることが次つぎと湧いてきます。子ども時代に「変わっている」と言われたこと、学級内ではグループに入らず「公平さ」を買われて学級委員長などにつかされやすかったこと、小学校3年頃から毎日のように地図ばかり見ていて、中学生になると辞書づくりに進んだこと、小説も書いていました。一人遊びゲームも自作していました。数え上げれば際限ないぐらいアスペルガー的特質で説明できることがあります。
私の子ども時代には社会的にはこのような視点はなかったのですが、看護婦だった母は兄弟5人のなかで私の異質性を認め、「特別支援家庭教育」をしていたように思います。》(『ひきコミ』第66号・2009年5月)にそのころ感じたことを書いたものです。
ある1つの作業に集中すると、それに熱中して他のことに気が回らない、ということは今もあります。一点集中と他への無関心はこうして両立するのです。一点への集中はある事柄に深く進入していく力になります。私が何かを感じ、それを進んでわかろうとするのはそこにあります。そしてわかったことを文章化する、それを積み重ねることが私のワーク(作業)になってきました。ワークはこの方法だけではなく他の方法もあると思いますが、私のばあいはこれによります。
アスペルガー障害の通説(?)とは違う感じをもつのがもう1つあります。周囲に起きていることを察知する力(感受性など)に疎いというものです。私の感覚では、よくわかるときとよくわからないときが際立っており、そのうちアスペルガー障害の通説では「よくわからない」が強調されていると思うのです。
《「一点への集中」と「他への無関心」》、そして《「よくわかるとき」と「よくわからないときがある」》という2つの事情は、その根っこは同じかもしれません。それを含めてこの2点が、私の子ども時代を書いたものにどのように表われているのか。あるいは表われていないのかも確かめられるのではないでしょうか?