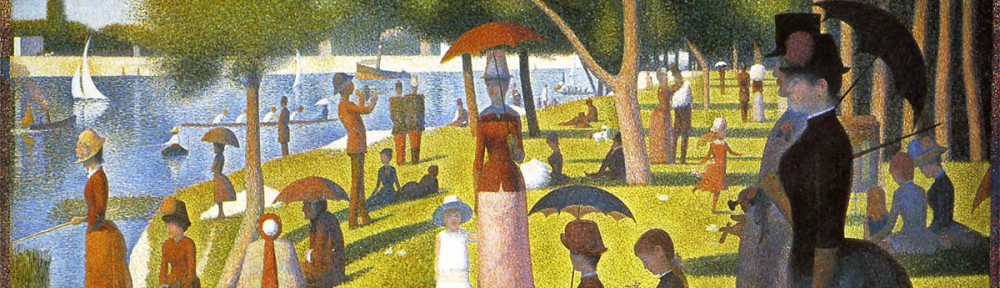私は介護の役割を家族の世代継承機能において高齢者(祖父母)世代、または介護を受ける側からも考えたいと思います。人に生まれ成長し社会を担い、そして高齢期を迎える。主に高齢期に介護を受けます。障害者など子ども時代から看護・介護を受けるばあいもこの家族の世代継承機能を担っていると推測します。
1つの論文を見ました。森川美絵「在宅介護労働の制度化過程——初期(1970年代~80年代前半)における領域設定と行為者属性の連関をめぐって」(大原社会問題研究所雑誌 №486/1999.5)です。私の求める目的に一致するとはいえませんが、〈介護〉が社会のなかで確立する経過を詳しく説明します。
指摘されたなかで4つの点が参考になります。
1つは、介護が本気で政策的課題になったのは1967年の調査で「70歳以上の寝たきり老人が全国に20万人以上もいる」(p27)と明らかになったことでしょう。
2つは、この介護をめぐり、初期は施設(入所)介護が重視され、それが在宅介護重視に徐々に移行していくこと。
3つは、非専門的な「主婦役割・大衆役割」化がすすみ、専門的な「特殊な技能・知識を要する行為」が対置され理解が動揺的でありつつ、今日に続いていること。
「負担を感じる家族それぞれに念頭される介護とは、病院への付き添い、食事づくり、尿道カテーテルや人工肛門の処置、公共の福祉制度の情報収集、そのような明確な行為として表現できない様々な気遣いや気苦労かもしれない。介護という表記法は、このような、介護という言葉で社会的に了解されるあいまいな行為領域を、あいまいなまま総体的に指示する表記法である」(p26)。
これは介護に限定されるのではなく家族内ケアの全体に通じるものと見ます。
4つは森川さんの論文では、それを乗り越えるために、介護の社会化、介護の地域社会化としながら、問題を抱えたままの現状を指摘しています。
*この論文発表の後1998年に、介護保険制度が制定されました。
一般家庭の家事労働としては、介護の手がたらずヤングケアラーの事態を生み出し、他方では「介護退職」という親の介護のために娘などが40代、50代の早期退職になる事態も生み出しています。
森川さんが表わしているのは介護を提供する側、介護を社会的に支える行政的視点からのものです。その意味するところは大切と思いますが、人の一生として介護を受ける当事者の視点は見当たりません。この点での何かを明示しないと、家族内ケアの構成部分である介護はよく理解できないのではないか。これが感想です。
一般に家族内ケアにおいて、それを受ける例——乳幼児期から成長期の子ども、成人の障害者、高齢の被介護者——の立場からも問題を見ないと、それが家族制度を動かす原動力である点は、十分にはないかもしれません。
私は上の仮説に近づくためにもう1つの論文を見ました。西川真規子「感情労働とその評価」(大原社会問題研究所雑誌 №567/2006.2)です。この論文には感情労働の事例として「在宅介護」が挙げられています。介護の質を高めるには「4つの気働き」があります。それは①感情的知性(自分と利用者の感情や立場を理解し…サービス実践に反映する能力、②〈メッセージ伝達や行動説明、問題解決策や利用者の説得なサービス実践に必要なコミュニケーションスキル〉、③感情管理スキル(ネガティブな感情を抑えヘルパーとしての適切な感情を維持するスキル)、④場の設定スキル(初対面での対処や利用者のニーズの把握など利用者との関係構築、共通の場の設定に関するスキル)です。
この4部分をサービスの質および介護に関する所有資格において調査しました。首都圏130の訪問介護事業所の545名のヘルパーを対象に実施されました。著者は「4つの気働きスキルとサービスの質は有無な相関関係がある」(p11)とし、また資格上の関係では「関連性は希薄である」としています。
私にはこれを判断できる能力はありませんが、調査した施設における介護士は、いずれにしても低くはないとの感想を持ちました。著者はこのスキルを高める「現状の資格講習システムでは、感情労働に関する能力・スキルの向上に十分に対応できていない」(p12)としています。
西川さんの論文は、対応する介護側の技量の点からのアプローチであり、当事者側からのものではありません。ただ介護を「感情労働」ととらえる見方は、実務的・ルーティン作業とは別の労働評価にあたります。知識集約型労働と対置する労働の性格をとらえています。
私が見た範囲では、介護を受ける側の意見は統計的に扱われる規模で集約されたものはまだありません。私が期待していることは介護を受けている側の状態・気持ちを多く見ることにより明らかにされるでしょう。総合において在宅介護の方が介護受給者にはいい環境にあると言えるでしょう。私のささやかな経験の範囲では、家族と切り離された入所型介護施設では介護が「世代継承機能の一部を担う」とする面を証明するには十分ではありません。