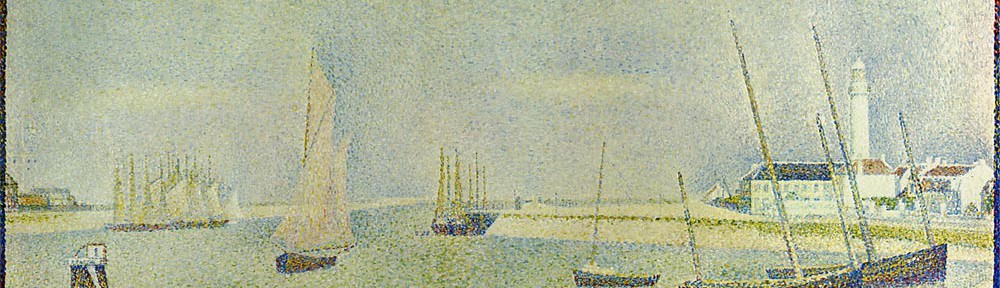ある日の午後に電話がありました。
その場にいた人と私は話し中なので、ゆっくり電話を聞く時間がありません。
そう告げたのですが、精神的にセッパ詰まった感じで電話主はこう言いました。
「じゃあ何か言ってください!」と。
「どういうこと?」
「私が元気になるような、勇気づけられること」
こういう要望に対して、私はうまい言葉が浮かびません。
そのときも何かを言ったのですが、つまらないことのはずです。
元気になるとか勇気づける言葉ではなかったことは確かです。
電話が終わった後、同席していた人に話しました。
「すごくわかりますね」それがこの人の感想です。
私と言えば「元気になるような、勇気づける言葉が出ないね。いや、僕はほめるのがへたなんですよ」と告白。
なぜなんだろう?
そう、その場を取り繕うような言葉を飾ってうまく切り抜けるやり方に嫌悪感があるのです。
当事者にはそういうその場かぎりの言葉ってバレバレじゃないですか(それでもないよりはいいという人もいますが…)。
一般人には通用する社交的な言葉は当事者にはしらじらしいものだとの思いがあるのです。
自分で実感していることしか話せない、話すべきじゃない。
私にはそういうのが心の奥にあって、その場にあった取り繕いの言葉を考えないようにしているのだと気づきました。
そういう“努力”をむなしく感じて放棄しています。実はこれも私の居直りの一つです。
私の“居直り”が無害なものであるとわかっていただけますか? そして自己肯定の形であることも…。
その日の深夜、午前1時25分、先ほどの電話主からメールが届いていました。
「甘えかたがわからない」という題になっていました。
あるカウンセラーさんとのいい体験エピソードが書かれていました。
そのメールを読んでいるうちに感じたことはこうです。
そうか、「甘えかたがわからない」が依存しやすい理由の1つかもしれない、と。
甘えられないのと依存するというのは対極にありながら、同じ心性の表われ方なんです。
両極端にあらわれる例です。
そしてこれはまた子ども時代にうまく甘える(依存する)ことができなかった後遺症でもあると思いました。
言い換えるとマルトリート症候群の1つの状態像かもしれません。
人は甘え(依存)を経験しながら、依存を抜けていくのです。
幼児期にうまく依存経験できないと成人後に依存的な様子を残していきやすいのです。
これには理由があり、私は成人後のこのような依存は必要だと思っています。
そのような依存できる対象が必要、という意味です。
それと並行して“対等な”人間関係を経験する必要もあります。居場所にはその役割があります。
依存や人間関係を経験しながら、人は依存の心性から抜けられるのでしょう。
わりと最近の出来事です。